はじめに
消化器外科の手術は時代とともに変遷しており、従来開腹手術だったものが1990年代の腹腔鏡の導入で小さな傷で低侵襲な手術が始まり、そして2008年のロボット導入以降ロボット手術がだんだんと増えているのが現状です。今回はそのロボット手術の日本の現状について解説していきます。
ロボット手術とは?
ロボット手術とは、医師が操作するロボットを使用して行う手術のことです。特に「ダヴィンチ(da Vinci)」と呼ばれる手術支援ロボットが有名ですが、最近は多くの国産ロボットも登場しており、ロボット同士の競争も始まっています。医師はこれを使うことでより精密な手術が可能になります。
ロボット手術のメリット
- 高精度な手術 従来の腹腔鏡では鉗子という道具を使用していました。この鉗子には先端を曲げられないという弱点があり、鉗子の入らない場所の手術は開腹するしか方法がありませんでした。しかしロボットアームの先端は曲がるように設計されたため、深く・狭い場所でも精密な手術が実現しました。
- 3D視野での手術 ロボットのカメラは直径8mmと細いですが、高精細な画像が得られるうえに術者が3Dで見ながら手術が可能です。そのため奥行きを感じながらの手術となり、体内の状況把握がより正確に行えるようになりました。
- 低侵襲で回復が早い ロボット手術の傷は腹腔鏡と同じく小さいため、開腹手術よりは回復が早くなりやすいです。
- 術者の負担軽減 従来の手術では手術着を着た上で立った状態での手術が通常でした。しかしロボット手術では手術着を着る時間はほとんどなく、また座ったまま手術ができるため、外科医の負担が減り、長時間の手術でも集中力を維持しやすくなりました。
ロボット手術のデメリット
- 費用が高い 例えばda Vinciは1セット当たり3億円とかなり高額であり、維持費も毎年数百万円かかります。一方で手術を行うことで収入となる手術費用は日本では安く設定されており、赤字ギリギリの手術を実施することになります。
- 触覚がない 従来の開腹手術や腹腔鏡は術者が直接道具を扱っていたため、腸の硬さなどを直接確かめることが可能でした。しかしロボットアームには触覚を検知する機能がなく、無理やりな操作で血管などを傷つけるリスクがあります。※昨年末に新たに触覚機能を持つ最新のロボットが発表されました。
- 専門的な技術が必要 ロボット手術を行うためには、内視鏡技術認定医という難しい試験をクリアした医師が1人以上必要になります。
ロボット手術の始まりと現状
日本におけるロボット手術は2008年にda Vinciを個人輸入(藤田医科大学、宇山一朗先生)し、2009年から臨床試験を開始したことで始まりました。その頃にはお隣の韓国でロボット手術が普及し始めており、韓国から医師を招いて指導をしてもらっていました。
その後消化器外科分野では様々な手術が保険収載されていき、現在では胃癌、結腸癌、直腸癌、膵臓癌、肝臓癌が保険収載されています。
またロボットも国産化が始まり、現在ではHinotoriやAnsurなどが実際に手術で使用されています。
現在稼働中のロボット一覧
da Vinci
日本で現在最も稼働しているのがIntuitive Surgical社のda Vinciです。日本に輸入されたのが2008年で、”S”が最初のモデルでした。その後どんどん進化し、現在は”Xi”という機種が大半を占めています。ここ数年では傷1箇所だけで手術が可能な”SP”や触覚機能を持った”5″なども登場しており、これからも進化を続けていくロボットです。

hinotori
hinotoriは日本初の国産手術ロボットであり、川崎重工業とsismexが出資して誕生したmedicariod社より出されています。アームの位置や操作はda Vinciに似ており、da Vinciでの手術経験がある医師にとっては操作しやすいロボットです。最大の特徴は遠隔での手術を実現している点であり、2023年に藤田医科大学とシンガポールを結んで行った操作実験では操作は問題なく行われました。やや操作の遅延はあったため、今後はそこの解決が課題となっています。

Hugo RAS システム
HugoはMedtronic社が開発した手術ロボットです。先の2台とは異なり、アームが1台毎に分かれていること、手術を操作するコックピットがopen型になっていることが特徴です。アームが1台毎に分かれているため、狭い手術室でも工夫次第で入れることができる点や、実際に手術を操作している画面を直接見ることができる点が有用とされています。ただ現状日本ではまだ稼働台数は多くありません。

Saroa
Saroaは東京工業大学と東京医科歯科大学(昨年統合し東京科学大学に)がリバーフィールド社と開発した国産ロボットです。このロボットの最も特徴的なのは触覚があることです。他のメーカーが開発段階の中でいち早く開発に成功しました。しかし他社とは異なりアームが3本のため、多くの手術で助手による操作が必要なところがやや難点です。こちらもopen型のコックピットです。

ANSUR
最後に紹介するのは朝日インテック社のANSURです。このロボットはいままで紹介してきたものとは概念が異なり、腹腔鏡手術で使用するロボットです。このロボットのテーマは”もう一人の外科医”であり、カメラと鉗子を人の代わりにロボットが持っている、いったイメージです。腹腔鏡を実施している病院ならどこでも導入できるのが利点ですが、執刀医自身も術野に入る必要があることが異なる点です。

まとめ
今回はロボット手術について紹介しました。今後もさらにロボット手術は増えていくことが予想されており、使用する機械の種類もさらに増えていくと考えられます。ロボット手術について少しでも理解を深めていただけたら幸いです。
ご質問があればいつでもお受けします!
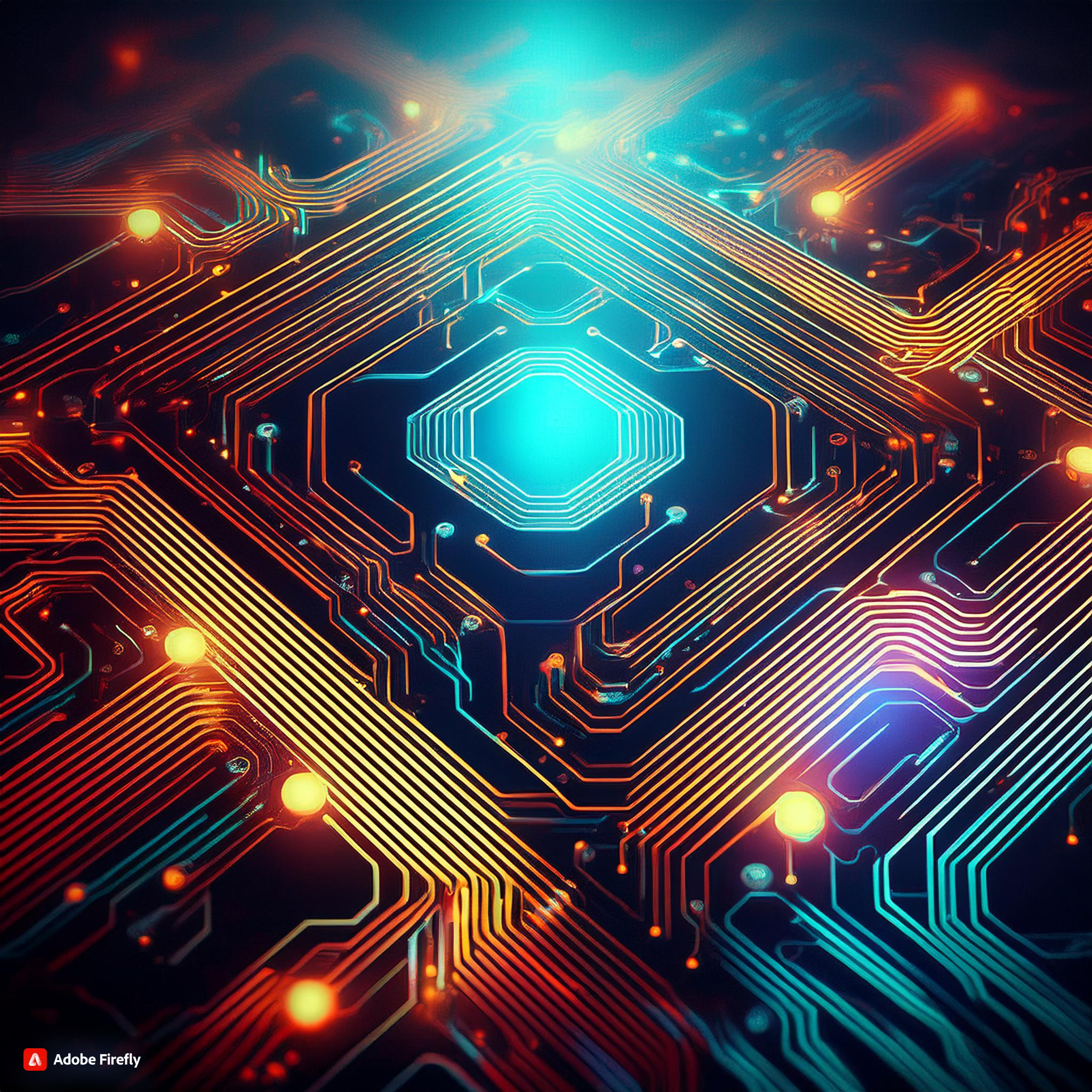


コメント